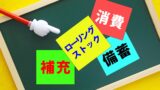「備蓄を始めよう!」と意気込んで準備したはずなのに、いざというときに役に立たなかった。
そんな経験や後悔をした人は意外と多いものです。防災意識の高まりとともに、非常食や保存水などの備蓄をする人は増えていますが、その内容や管理方法を間違えてしまうと、せっかくの備えが無駄になってしまうことも。
備蓄初心者がつまずきがちな「5つの落とし穴」と、その具体的な対策を分かりやすく解説します。
これから備蓄を始める方や、すでに始めたけれど見直したい方向けの記事になっております。
備蓄初心者が陥るありがちな5つの失敗例とは?
備蓄を始めたばかりの人がよく陥る失敗には共通点があります。
たとえば、
- 賞味期限が切れていた
- 必要な物が揃っていない
- 保管場所が不適切
- 家族構成に合っていない内容
- 非常時に使い方が分からない
などなどありがちな失敗は意外と多いと思います。
せっかく備えていても、いざという時に使えなければ意味がありません。こうした落とし穴を防ぐためには、日頃から見直しや練習を重ねることが大切です。
では早速チェックしていきましょう!
賞味期限・使用期限の管理ができていない
「気づいたら非常食がすべて期限切れだった」「保存食を処分する羽目に…」というケースは、備蓄初心者の中で最もよくある失敗です。
※余談ですが、私も過去にやってしまいました(笑)
長期保存可能な食品でも、永久的に持つわけではありません。特に乾パンやアルファ米、レトルト食品は意外と期限が短く、数年でダメになるものもあります。
おすすめの対策方法とは?
期限一覧表の作成する
ノートやスプレッドシートに賞味期限を記録し、見える化するだけでかなり防げます。ここでポイントになるのが「見る」という事です。表を作っても目の見えない場所に保存していると意味がありませんので、紙であれば冷蔵庫に貼る、データなら見えるところに保存しておくという事が大切です。
スマホのカレンダーでリマインダー設定
期限の数か月前に通知を出すことで、買い替えのタイミングを逃しません。リマインダーが来てもすぐに行動を起こさないと忘れてしまうので後回しにせずにすぐに行動しましょう。
毎月1日は“備蓄チェックデー”に
定期的な確認習慣を持つことで、食品のムダや買い直しを防ぐことができます。備蓄確認の習慣化ができればもうあなたは備蓄のプロです。
盲点!?水の備蓄が圧倒的に足りない
意外と盲点なのが水です。
食料は意識して買いそろえたけど、水の量まではしっかり計算していなかったという方が意外と多いです。
私達は蛇口をひねれば水が出てくるのが当たり前だと思っていますが、ライフラインが止まってしまう災害なども想定しておかないと備蓄の意味がありません。
また「家族全員分の水ってどのくらい必要なの?」と疑問に思いながらも、2〜3本のペットボトルで安心してしまう事もありますよね。ここでしっかりと水の備蓄量を理解しておきましょう。
おすすめの対策方法とは?
基本は1日1人あたり3リットルが目安:飲用+調理+衛生用と考えると、最低でも3日、できれば7日分あると安心です。
家族の人数分を掛け算で計算してみましょう。
たとえば4人家族なら、3L×4人×7日=84L。2Lペットボトルで42本です。
調理・トイレ・手洗いにも水は使います。水は“飲むだけ”ではありませんので、多めに備えるくらいがちょうどよいと考えておきましょう。
加熱や調理の手段を考えていない
「レトルト食品や乾物を用意したけれど、火もお湯も使えなくて食べられなかった」というのは災害時によくある話です。
特に電気やガスが止まることを前提に準備していないと、食料の意味がなくなってしまいますので注意が必要です。
オール電化住宅などでは、電気が止まるとすべてのライフラインがストップしてしまう事があります。
おすすめの対策方法とは?
カセットコンロ+ガスボンベを最低3本以上備蓄しましょう!
商品にもよりますが、1本のガスボンベで約60分カセットコンロが使用可能なのでお湯を沸かすなどができますし、調理も可能です。
複数日を想定して準備をしておくと良いでしょう。
そのまま食べられる食品も用意する
缶詰(サバ・ツナ・おでん)、クラッカー、乾パンなどは火を使わなくてもOK。あと水を売れるだけでお米を食べられるアルファ米商品などもおすすめです。
LEDランタンや電池の備えも!
停電時の夜間調理・トイレ利用などにおすすめです。乾電池式・充電式の2種類があると安心です。またスマホ充電用のバッテリー式充電器やソーラーで充電できるタイプの乾電池なども備えてあるとなお良しです。
家族構成やライフスタイルを考慮していない
非常食をそろえて満足していたけれど、いざ開けてみると、
- 「子どもには味が濃すぎる」
- 「祖父母には硬くて食べられない」
- 「アレルギー表示を見落としていた」
など、家族全員に対応できていないケースは意外と多いのです。
おすすめの対策方法とは?
子ども向けのお菓子やミルクも備える
これは子育て中のご家庭の場合ですが、子供向けの食料などを備えておくと良いでしょう。子供は不安になり精神的に不安定になってしまう事もありますので慣れ親しんだ味があるだけで安心感が違います。
高齢者向けのやわらか食をチェック!
高齢者と同居している場合は、高齢者用の食料の備えも必要です。おかゆ、ゼリータイプの栄養食など、食べやすさを重視しておくと良いでしょう。
アレルギー対応食品の確認しましょう
ご家族の中にアレルギーを持っている方がいる場合には備蓄にも注意が必要です。備蓄食料の成分をしっかりと確認して備えるようにしましょう。特に小麦・乳・卵アレルギーには注意し、代替食も一緒に用意。
ペット用品の備蓄も忘れずに
ペットを飼っているご家庭の場合は、ペット用の備蓄も忘れずに。フード、トイレシート、飲料水など、ペットの命綱も一緒に考えましょう。
「どこに何があるか」を把握できていない
せっかく備蓄をしても、いざという時に、
- 「どこに何があるか分からない」
- 「非常持ち出し袋が見つからない」
となると意味がありません。
とっさの行動が必要な場面では、探す時間すら命取りになりかねません。
おすすめの対策方法とは?
アイテム別にカテゴリー整理する
ローリングストックという観点から備蓄を見てみると「食料」「水」「衛生用品」「医療品」「照明系」などカテゴリーで分けると管理しやすくなります。
保管場所は家族全員で共有する
家族で備蓄情報を共有する事はとても大切です。子どもでも分かるようにラベルを貼るなど工夫しましょう。
また持ち出し用と自宅待機用を分けておくなどもあれば良いでしょう。避難時に持っていく用と、自宅で生活する用を明確に分けると混乱を防げます。
まとめ
備蓄は、ただアイテムを買いそろえるだけで終わりではありません。日々の生活の中で定期的に見直し、使い方や保管方法まで含めて「運用すること」で、本当の意味での備えになります。
今回紹介した5つの落とし穴は、どれも初心者が陥りがちなポイントばかり。しかし、知っておけばすぐに対応できるものばかりでもあります。まずは身近なところから。今日、キッチンや押し入れを見直して、水や食品がきちんと揃っているか確認してみましょう。
そして、「この備蓄は本当に自分や家族のためになるか?」と一度立ち止まって考えることが、将来の安心に直結します。日々の暮らしの延長線上に、災害への備えがあります。無理なく、少しずつ、あなたらしい備蓄スタイルを整えていきましょう。